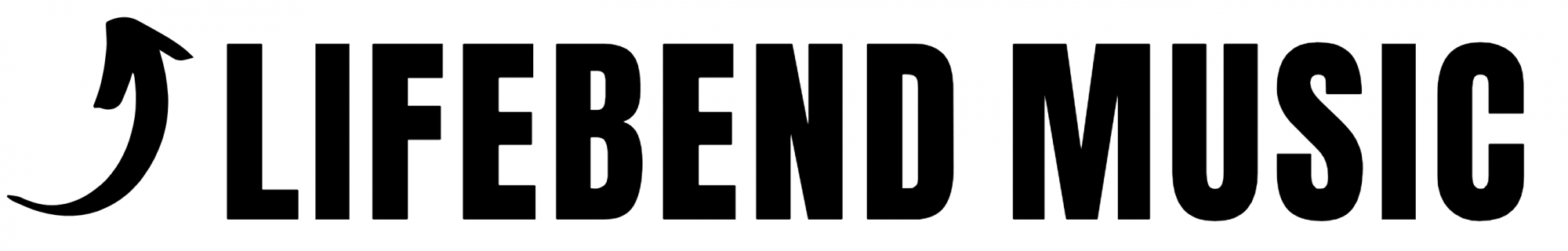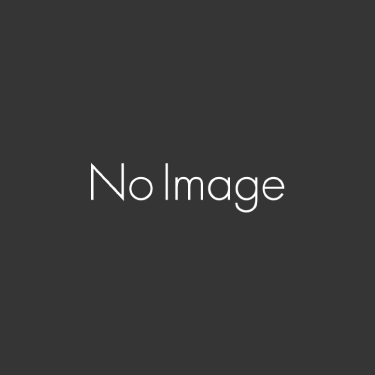岡聡志のレッスンが受けられる『岡聡志MGL』のレッスンの一部を抜粋してお届けします。
聴きやすいセクションの重要性
今回は僕の作曲におけるプロセスや大切にしていることについて話していきたいと思います。
曲を作る時に、テクニックをたくさん使った難解なセクションをとり入れたいと言う人も多いと思います、そして難しいセクションが多くなれば多くなるほどメリハリが無くなってしまう場合もあるので注意が必要です。
リスナーとして難解なセクションを聴き続けるとやっぱり「なんか難しいなあ??…」「なんかふわふわしてて落ち着かないなぁ~」ていうところがなんやかんやあると思います。僕自身も曲を聴く時に、小難しくてイージーリスニングできないセクションばっかりが続く曲を聴くと楽曲としての印象が薄くなってしまいます。
本日のレッスンで題材にしている僕のオリジナル曲は、そのあたりのメリハリをつける目的でA、Bは難しく、サビは分かりやすいコード進行、メロディを持ってきています。。
分かりやすいセクションの次がまた元の難解なコード進行に戻る感じです。
(模範演奏)
ここから元の難しいコード進行に戻る感じですね。いかがでしょうか!
曲の印象を変えていく
また1曲を通して印象が変わらなすぎると楽曲的には良くないので、同じメロディーだったとしてもバックグランドは変化を加えてあげるっていうのも非常に大事です。
また、変化の度合いにもよりますが、あまりに変化が大きすぎると世界観が統一されてない感じも出ちゃうのでバランスが重要です。あまりにもギャップがありすぎてそれを受け入れられないっていう人ももしかしたら中にはいるかもしれないです。
やっぱりこの難しくするっていうのは結構塩梅が難しいというか。難しい難しいってもう全部が難しいね。言葉が!笑。
なので基本的にイージーリスニングできるセクションが存在するというのは聴きやすい曲を作るという上でものすごく大事だと考えています。僕が作曲する上で特に大事にしてるポイントです。
難しいと聴きやすいのバランス感覚
僕が影響受けてるアーティストでブラッド・メルドーっていうピアニストがいます、そのピアニストの楽曲はものすごくメロディックなのにアウトも物凄いんですね。えげつないアウトの響き、対照的なメロディックなセクションもしっかり楽曲に取り入れられてるのでメリハリをすごく意識してらっしゃるなというのを感じます。僕はそういった曲が凄く好きですね。
難しいところがありながらも、ちゃんとシンプルに聴けるメロディーのセクションをつけようという意識は普段からあります。これから作曲される方、既にされてる方への参考になれば幸いです。
★ここがポイント!
難しいセクションも、聴きやすいセクションがあるからこそ引き立つ!作曲する上ではこの両者のバランス感を意識してみよう!
一般公開はここまで。MGLでは岡聡志のデモ演奏も交えて、モダンなギタープレイのレッスンを配信しています!
皆さんが更に音楽を楽しむきっかけになれば幸いです。
オンラインサロン『岡聡志MGL』では、岡聡志による月2回のレッスンが受けられます。更には、レッスン以外にも会員同士のコミュニケーションや雑談配信などもあり、充実した内容になっております。
現在40名以上が在籍中のMGLで、岡聡志と一緒に楽しくモダンギターを練習してみませんか?
今よりもっと上手くなりたいけど、きっかけがない、周りにレッスンを受ける環境がない!そんな方は是非参加をご検討ください。